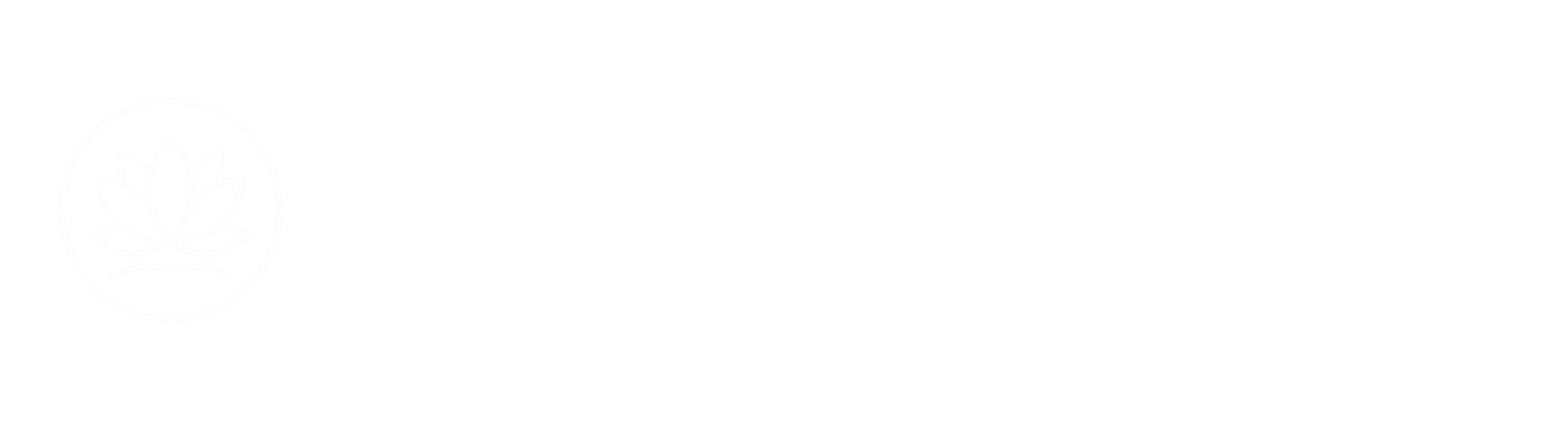信解品第四を4回に分けて連載します。信解品は、法華経の「意味」を分かりやすく掴むうえで、非常に重要な章です。ここでは、長く修行して「自分はもう悟った」と思い込んでいた弟子たちが、釈尊が舎利弗へ授けた授記(成仏の予告)を目の当たりにし、心の深層が揺さぶられます。これは「救いが一部の人だけのものではなく、一乗(すべての人が救われる道)へ回収される」という宣言の始動でもあります。
さらに「長者窮子の譬喩」が始まり、救いは力でねじ伏せるものではなく、相手の心の器に合わせて段階的に導く方便として働くことが示されます。同時に、臆病さや劣等感が心を支配すると、救いから逃げてしまう――その逃げ癖自体が業(ごう)となる、因果応報の厳格さも描かれます。甘い慰めではなく、覚悟を要求する慈悲。そこが、法華経の核心です。
老いた四人――「火は消えた」と言い切った私たちの胸が、いま燃え直す
その時、四人の老人が立ち上がった。 慧命須菩提。摩訶迦旃延。摩訶迦葉。摩訶目腱連。
かつて教団の柱と呼ばれ、今は枯れ木のように静まり返っていた長老たちだ。 だが、その瞳には奇妙な熱が宿っていた。老いの灰を吹き飛ばすような、若々しい炎だった。
彼らは、聞いたのだ。 舎利弗への授記。 「お前は仏になる」という、逃げ場のない約束を。 その瞬間、彼らの内側で、錆びついた骨が軋みを上げて鳴った。
彼らは衣を正し、右肩を露わにし、膝を突いた。 それは儀礼ではない。五体投地に近い、魂の土下座だった。
「世尊よ。私たちは、自分たちを『上がり』だと思っていました」
代表して語る摩訶迦葉の声は、乾いていた。 私たちは、煩悩の火を消した。痛みへの執着も、喜びへの渇望も捨てた。もう何も求めない。何も望まない。 それが悟りだと信じていた。 だから、世尊が菩薩たちに「世界を救え」「無限の力を得よ」と説いても、心は動かなかった。 「ああ、それは若い人たちの仕事だ」と、特等席で眺めていただけだった。 私たちは救われた。だから、もう終わり。 その「終わり」という安堵が、いつしか老いた心の鎧になっていたのです。
だが――舎利弗への言葉を聞いて、鎧が砕けました。 求めてもいないのに、突然、巨大な宝石を投げつけられたような衝撃。 「お前たちもだ」と言われた気がしたのです。 私たちの旅は終わっていなかった。いや、始まってさえいなかった。
歓喜と、恥辱。 その二つがない交ぜになった感情を説明するために、彼らは教えを求めた。
「もっと聞かせてください」
仏はある男の物語をゆっくりと話し始めた。
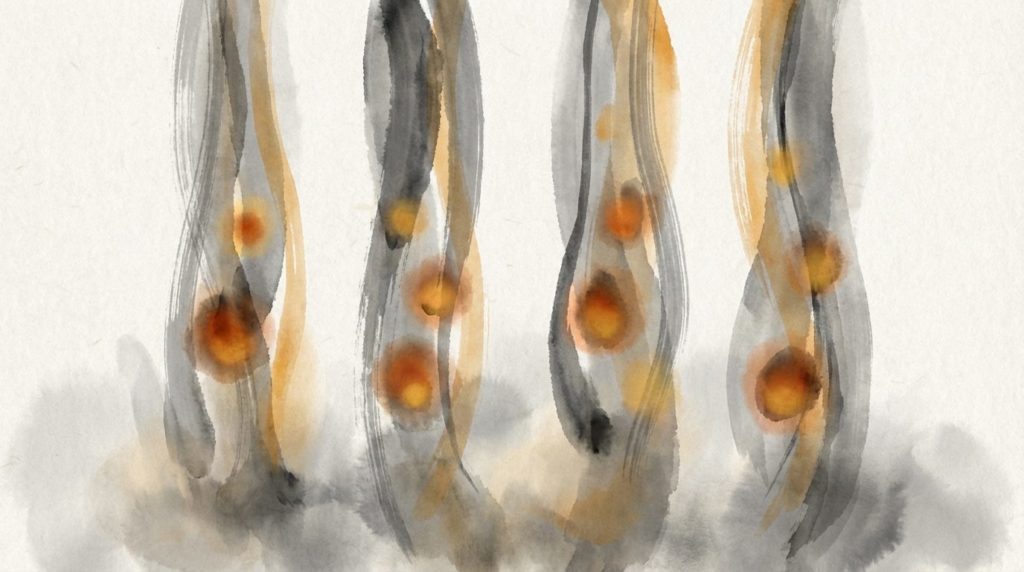
長者窮子――五十余年の放浪と、王のような父の静寂(しじま)
ある男がいた。 幼い頃、彼は父を捨てて家出した。 理由はわからない。若さゆえの反抗か、あるいは自分の力を試したかったのか。 彼は他国を放浪した。十年、二十年、五十年。 年月は彼を大人にしたが、同時に彼を削り取った。貧困。飢餓。裏切り。 かつてのプライドは消え、残ったのは「今日をどう生き延びるか」という卑屈な習性だけだった。 彼は仕事を求めて、偶然、ある町へたどり着いた。
そこには、一人の大富豪が住んでいた。 父だった。 父はずっと子を探していたが、見つからず、この町で商売を成功させていた。 その富は国家予算に匹敵する。金銀財宝で満ちた蔵。無数の使用人。象や馬の列。 だが、父の心には穴が開いていた。 ――私には後継ぎがいない。 死ねば、この莫大な財産は霧散する。あの子さえいれば。あの子にこれを譲ることができれば。 それは執念に近い愛情だった。
ある日、放浪者は偶然、父の屋敷の門前に立った。 彼は中を覗き見た。 獅子の座に座り、宝石で飾られた服を着て、多くの家臣にかしづかれている老人。 圧倒的な威厳。まばゆい光。 それを見た瞬間、放浪者は思った。
――やばい。逃げよう。
彼は気づかなかった。それが父であることに。 彼が見たのは「親」ではなく「王」だった。 ここは俺のような人間が来ていい場所じゃない。捕まれば殺されるか、奴隷にされる。もっと貧しい里へ行こう。そこなら残飯にありつける。 彼は背を向け、走り出した。

父は、一目で気づいた。 あの子だ。五十年間、夢にまで見た息子だ。 父は歓喜し、部下に命じた。
「あいつを連れて来い!」
使者が走る。追いつく。腕を掴む。 放浪者は絶叫した。
「俺は何もしてない! 放してくれ!」
だが、使者は無理やり引きずる。 放浪者の脳内で、恐怖が炸裂した――殺される。 罪もないのに捕まった。これは処刑だ。 あまりの恐怖に、彼は白目を剥いて気絶した。
父は、遠くからそれを見て、悟った。 ダメだ。 あの子は、心が卑しくなりすぎている。 今のあの子に「私が父だ」と名乗っても、信じないだろう。それどころか、罠だと思って逃げ出すかもしれない。 父と子という関係は、血だけでは成立しない。魂の高さが揃わなければ、愛は恐怖にしかならないのだ。
父は、部下に命じた。
「水をかけて正気に戻せ。そして、放してやれ」
何も言うな。私に関わるな。 父は、名乗ることを諦めた。それが、今できる唯一の慈悲だったからだ。
解放された放浪者は、命拾いしたと喜んで、貧民街へ消えていった。 父はそれを見送りながら、長い溜息をついた。 そして、作戦を変えた。 正面突破は無理だ。ならば、あの子のレベルまで降りていくしかない。
父は、二人の部下を呼んだ。 人相が悪く、薄汚れた格好の二人組を。
「行って、あいつを雇ってこい。『いい仕事があるぞ。便所掃除だ』と言ってな」



■ 主な参照文献
- 『現代語訳 法華経』(2025年11月刊」)
創価学会教学部 編(聖教新聞社)
※本文の構成・現代語訳・語義理解の確認に使用 - 『法華経(上)』
坂本幸男・岩本裕 訳注(岩波文庫、岩波書店)
※サンスクリット原典の構造および仏教用語の学術的確認のため参照 - 『妙法蓮華経 並開結』
(鳩摩羅什 訳)
※漢訳原典に基づく章構成・ストーリーの流れの確認に使用